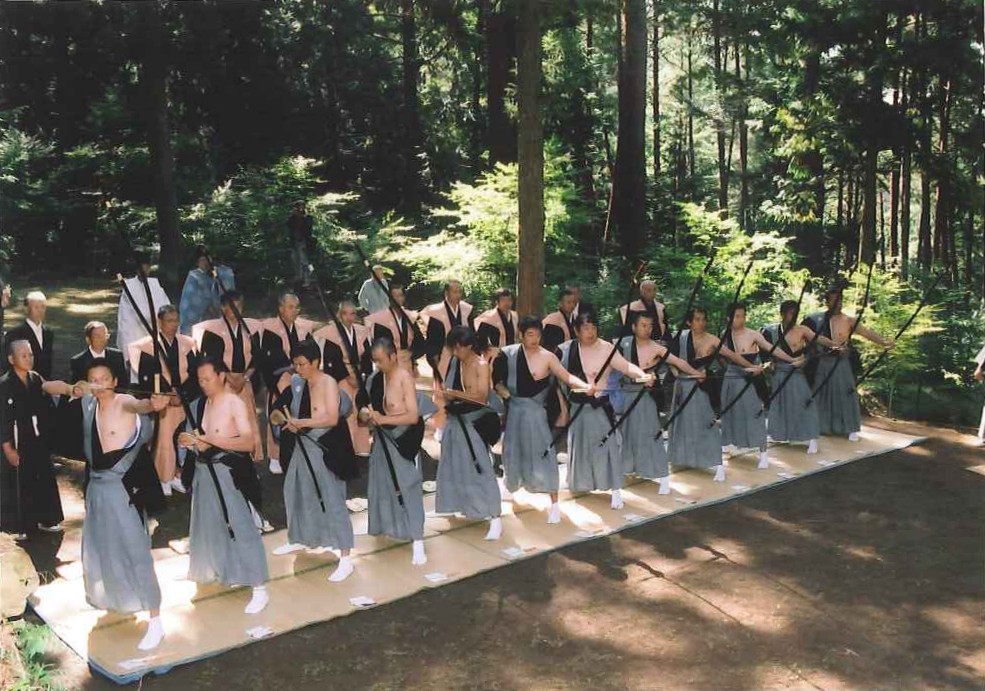本年も「あるぷす不動産」をよろしくお願いいたします。
「家を持ちたいのであれば、地方へ移住するしかない」
建築費の高騰は、地方移住を現実化させています。平均年収が460万円(国税庁・令和5年分)のままでは、なおさらです。
この際、2026年は移住計画元年として、家族が自然の中で暮らす未来像を描き始めてはいかがでしょうか?
そして、どうせ田舎へ移住するのなら、「長野県」は人気・実力共に、とても魅力的です。
* 九州のお医者さんから知った、日本人にとっての「長野県」
40年前、九州で医者にかかった時です。
カルテの住所を見るや否や、お医者さんは開口一番に言いました。「おっ!君は長野県から来ちょんかぇー。長野県の景色は別格やねー。ほんま、スイスにおるんかち、思うたとよ。」
「教養のある人は違うな」と思いました。九州では長野県と言われてもピンッと来ない人ばかりのようで、決まって「田舎やろ?」としか聞き返されてこなかったものでしたから。
同時に、日本人からも長野県はスイスと同一視されている事を始めて知り、驚いた瞬間でもありました。
それから10数年後、冬季オリンピック開催により、「NAGANO」は世界が知る「ブランド」になりました。
** もはや、都心近郊では家を持てない現実
とある都心近郊の住宅街では、130坪の古い家屋が取り壊されて3区画に分けられました。そこには、31坪の小さな建売り3棟が完成。よくある話です。
場所も良く、駐車スペースも1台分ありますから、「すぐに売れるだろう」誰もがそう思ったに違いありません。ところが、販売価格は驚きの8,500万円~となりました。
銀行の住宅ローン審査が通る人は、年収1,700万円以上の高所得者です。
しかも、それほどの高所得者が買える新築とはこれか…と、現実の厳しさを思い知らされます。

*** どうせ田舎に暮らすなら、「NAGANO」そして駒ヶ根
人生って、案外「あきらめ」から大きく動き出すものかもしれません。
思い返してみてください。進学先をあきらめ、就職先をあきらめ、思い通りには行かなかった先で出会った友人や恋人、趣味、妻と夫。
家を持つことが理由で都会を離れ、駒ヶ根に移住したとしても、それは心豊かな生活の始まりになるかもしれません。
「超寒い~!」と文句を言いながらも、一足先に駒ヶ根へ移住された皆様は笑顔で暮らしています。見上げる中央アルプス・南アルプスも、まだまだ年間数㎜づつ隆起して成長しているのです。この地で、家族も共に成長する未来を想像してみてはいただけませんか?
駒ヶ根はどこよりも風光明媚な上、不動産価格は県内でもリーズナブル。
たとえ「家を持つ」為に選んだ駒ヶ根だったとしも、それは楽園生活の始まりかもしれない…そんな魅力を秘めているのです。