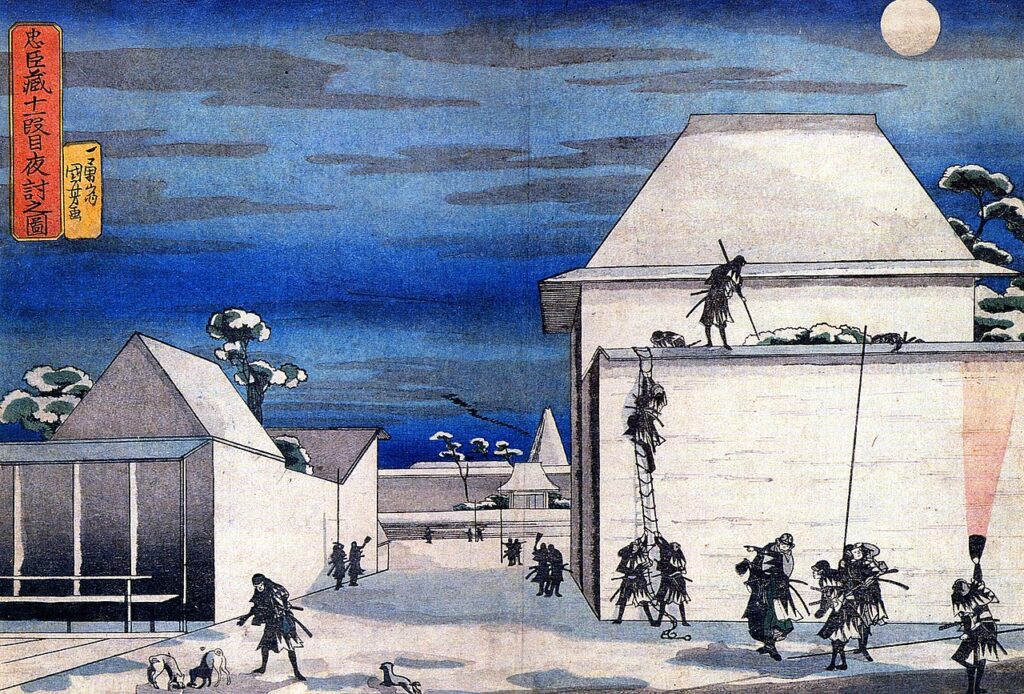7月5日は平穏無事だった駒ヶ根です。
「7月5日」の大災害説によって、むしろ長野県や駒ヶ根市は得をした側でした。稼ぎ時の夏シーズン、レジャーへ向かう先が山岳方面になったのは間違いはなく、観光産業を生業とする駒ヶ根市にしてみれば「ありがた山の寒がらす」でございました。
先日、東京都心は六本木界隈の蕎麦屋さんで「ソースかつ丼」のメニューを見つけました。
今回の長野県旅行でも、駒ヶ根名物「ソースかつ丼」を口にされた方も多かったでしょうから、またこうして本場のソースかつ丼の味覚体験者が増え、そして東京へおみやげ話を持ち帰っていただければ、六本木の蕎麦屋さん以外でもソースかつ丼の輪が広がるっていう寸法です。
重ね重ね、今回の「エンターテイメント」は駒ヶ根市にとっては追い風でした。
(エンターテイメント)
さてただいま、今回の「大災害説」のことを「エンターテイメント」と申しました。
マスコミの皆様はこれを「SNSによる科学的根拠のない陰謀説、嘘・デタラメ」と称して、一刀両断にされました。ところがこれの本質は、約1年間に渡る「エンターテイメント」だったことを見誤っておられるのではないかと思います。
オカルトファンから端を発したこの一件は、ユーチューバ―が食いつき、芸人が話術で話を拡げ、そこへ霊能力者やジャーナリスト、はたまた物理学者や大学教授、寺の住職までをも巻き込んでの一大「エンターテイメント」に発展したものです。
100人に5人が興味を持ったと仮定しても、実に622万人のマーケットを相手にしたエンターテイメントビジネスだった為、再生数も伸びるは、収益も上がるはで、大いに盛り上がった次第です。
(社会が不安定な写し鏡)
オカルトファンのみならず、思いがけず、一般の人々までをも騒動に巻き込んだ理由は、日本に満ち溢れる不安心理の表われでしょう。
阪神淡路、東北(地震・津波・原発)、能登半島と、現代日本人は辛い自然災害を経験しました。もうこれ以上は乗り越えられないのではないか?と、誰もが災害に怯えています。この一件が過剰に熱を帯びてしまったのは、今の日本社会が不安定で脆く、今にも心が折れてしまいそうな心理状況、その「写し鏡」だったように思います。
(もはや、人々の行動の源泉はSNS)
もはや、SNSが人々の生活に浸透しきっていることが浮き彫りになった今回の一件。その牽引役はYouTubeでした。
「日付を特定した予言など当たらない」と、誰もが理性的にそう思いながらも盛り上がって楽しんで、ちょっと不安に包まれたり、長野県へ旅行したり、駒ヶ根でソースかつ丼を食べたり、空のペットボトルに水を詰めて流しの隅にしまったりしたように、人々の行動の源泉は、SNSが中心的な役割を担う時代です。
TOYOTAの広告費もテレビからSNSへと移っているそうですから、それはとても自然な流れです。しかし、そんな変化する社会構造を許せない方々がいて、「SNSを規制すべきだ」とか言い、スマホをいじる国民をまるで「馬鹿扱い」していることも、これまた多くの国民がSNSから情報を得ているのです。

駒ヶ根ソースかつ丼「すが野」 TEL 0265-96-7701 菅の台バスセンター上