先日、山梨県内を走行中、「心地よい空間」に入りました。何かが違う…その通りには電柱・電線が無いことに気付きました。しかしその時に強く思ったのは、観光立国を掲げる長野県こそ「無電柱化の先進県」であってほしいという願いです。
もちろん長野市では、善光寺参道や市街地の多くで電柱・電線はありませんし、松本市でも駅周辺や松本城周辺は無電柱化されています。2つの地方都市は、日本を代表する門前町と城下町のため、市街地の再開発スピードも速く、連動して無電柱化を行えた背景があります。
一方で、他の県内市町村ともなれば、とてもそんな訳には行きません。
しかし、印象的なのは「しなの鉄道」沿線の街は、無電柱化された駅前通りが多いという事実です。きっとその背景には、長野北陸新幹線の開通と引き換えに信越本線をJRが手放すことによる街の衰退に危機感を抱いた市民と行政があったのでしょう。官民が一体となった「強い意志」による無電柱化事業が行われたのではないかと推測します。=長野市の篠井駅前通り=千曲市の矢代駅前通り=上田市の駅前通り=小諸市の駅前通り=は、無電柱化された清々しい景観を見せています。
白馬村駅周辺では、2年がかりの無電柱化工事が現在進められています。世界に誇るスノーエリアにとっては大変有意義であり、これが長野県内全域へと波及すれば、ヨーロッパの山岳風景にも負けないNAGANO,JAPANに生まれ変わることでしょう。
さて、駒ヶ根市はどうなのでしょうか?
実は「駒ヶ根ファームの前面」と「JR駒ヶ根駅の前面」の極々狭い場所での無電柱化にとどまっているのが現状です。ほぼ進んでいない残念な気持ちと、同時に財政が乏しい駒ヶ根市では仕方ないか…とのあきらめ気分が交錯します。
大きな自治体では、「無電柱化推進計画」なる特化した事業計画が存在しますが、駒ヶ根市には未だ存在しないようで、どうにか見つけた資料を要約すると「市街地の再開発を進める時には、無電柱化も同時に行いましょう」といった副産物的な内容で記載されるに留められています。
東南海沖地震が発生した際は、多くの電柱が倒れ、絡まった電線が避難者や救助の行く手を阻むでしょうから、無電柱化には「防災」の側面もあります。
電柱・電線の無い、澄み渡った景色の、そんな駒ヶ根の未来が早く訪れることを期待してやみません。

(多くの場合、この様に電柱と電線が映り込んでしまうのです…)








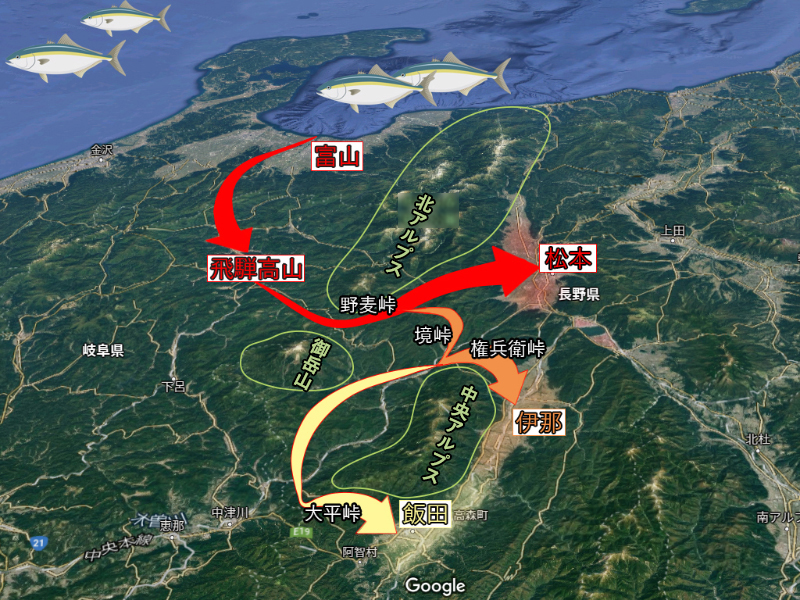
 画像場所/
画像場所/